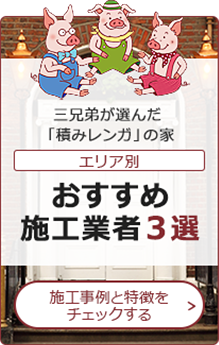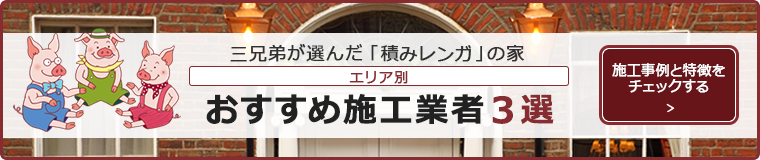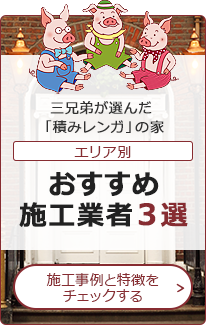幸健ホーム
注文住宅の幸健ホーム
レンガの家の事例を大調査
幸健ホームの特徴
木造軸組と鉄筋入りレンガ積みのハイブリッド構造
幸健ホームのレンガの家は「高耐久木造軸組みと鉄筋入りレンガ積みのハイブリッド構造」が特徴。在来工法と耐力面構造を合わせ、耐震金物で強さを増した「高耐久木造軸組み工法」を基本としています。
そのベースの外側にレンガを組み合わせていきます。レンガを積み上げていくのは、レンガ積みを専門としている職人です。
1棟の住宅で使うレンガはおよそ1万個。地震への耐久性に優れている高耐久木造とレンガという外壁を手に入れることで、より強固な家づくりを実現しました。
セラミックレンガ(断熱・耐火レンガ)を使用
これまでの耐火レンガは800℃以下の熱で焼かれたレンガを指していました。日本にあるレンガ造りの建物で有名なものといえば東京駅が挙げられるでしょう。
現在、幸健ホームでは断熱・耐火性の高いセラミックレンガを使用しています。焼きあがる温度は1,150℃と高く、セラミック化することで硬く丈夫になりました。
呼吸する家
幸健ホームの家は、レンガをはじめ調湿機能を持つ自然素材を多く取り入れた構造で、家が自ら湿気を排湿します。
高温多湿の環境は家にとって一番の敵である湿気が発生しやすい状態です。湿気はシロアリやカビ、木を腐らせる腐朽菌などを呼び込み、住宅寿命を縮めることにもつながります。これらを家自らが呼吸できる環境を作り出すことで回避しているのです。
構造・工法でも湿気を逃がす取り組みを欠かしません。例として地面からの湿気が来るのを防止するコンクリートベタ基礎工法、床下の湿気が溜まらないようにするための高い床高を設ける基礎パッキング工法、壁体内の湿気を外へ出す壁体内通気層工法なども呼吸する家づくりにつながります。
本物の健康住宅を追求
幸健ホームでは、家は自然素材を使って健康的な生活ができること、家が朽ちない対策が取られていること、資産価値が高いことの3つを意識して家づくりを行っています。
このこだわりを持って、100年以上耐える素材と頑丈な構造を採用。時代に左右されない見ばえで、住む人の価値が上がる家を追及してきました。
さらに住む人が健康になるように研究する「住医学研究会」にも所属するなど、家に住む人の幸せについて追及し続けています。
素材だけではない「エコ住宅」への取り組み
素材にこだわるだけでなく、環境問題にも着目している幸健ホーム。年々深刻化する環境問題に着目し、自然と人が住居を通して共生できることをコンセプトにしています。
電力は太陽光発電システムを採用する、又は生活用水も貯めた雨水を浄水化し、トイレや野外への散水などに再利用するシステムを導入するといった「エコ住宅」を広めています。
この取り組みは2005年に「太陽光発電と雨水の再利用を兼ね備えたエコ住宅の提供」という枠組みで、沖縄県から承認を受けることになりました。
家の美しさだけでなく、自然と共存する家づくりにも力を入れていることがうかがえます。
対応施工
木造軸組工法
幸健ホームが提供している耐久性の高い木造住宅「自然素材の家」の工法は、木造軸組み工法です。
木造軸組みの大きな特徴は、ほかで建てられている木造住宅の工法が壁という「面」で構成されているのに対して、梁や柱などの「線」で構成される構造になっていることです。
木を変形させるのは、材木に含まれる水分。天日で自然乾燥させた状態では、水分は40%ほど残っています。つまり、家の耐久性にとって肝心なのはひび割れの有無よりも十分に乾燥させた、強く変形しにくい木材を選ぶことなのです。
幸健ホームは家の強さの基になる構造材に、含水率を20%以下に低減した「かごしま高規格材」を使用しています。
標準施工でも住まいとしての安全性に細かい配慮
住まいの安全性を高めるため、主にシロアリの防止と災害に対する備えに力を入れています。
シロアリ防除のために行っているのが、土壌処理を施し防湿フィルムを敷き詰めてコンクリートを打設する「鉄筋コンクリートベタ基礎」です。
「基礎パッキング工法」もシロアリ防止、腐敗防止に効果を発揮します。これにより、機器を使った強制的な換気が必要ではなくなります。
台風いや地震などの自然災害に効果を発揮するのが「補助金物」です。「ウッディストビーム工法」は梁の間隔を短くすることにより、建物の強さを高めます。
そのほかにも空気中の湿気を放出するシートを用いた「壁体内通気層工法」や省エネと強度・耐久性のアップがのぞめる「床二重張り施工」なども標準施工となっています。
幸健ホームの基礎情報
会社名
株式会社 幸健ホーム
所在地
那覇市銘苅2-10-1